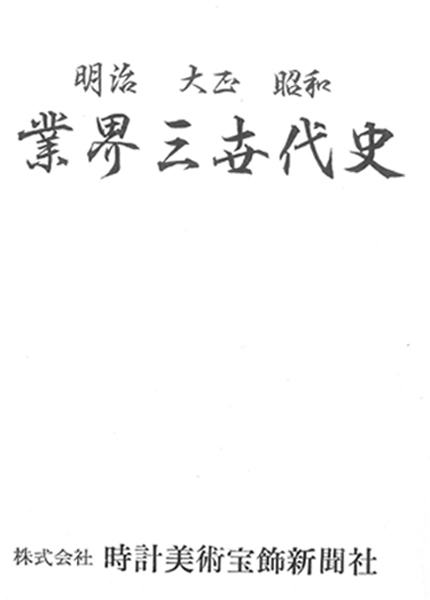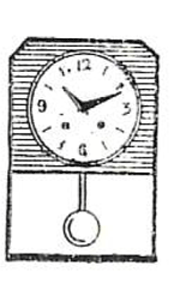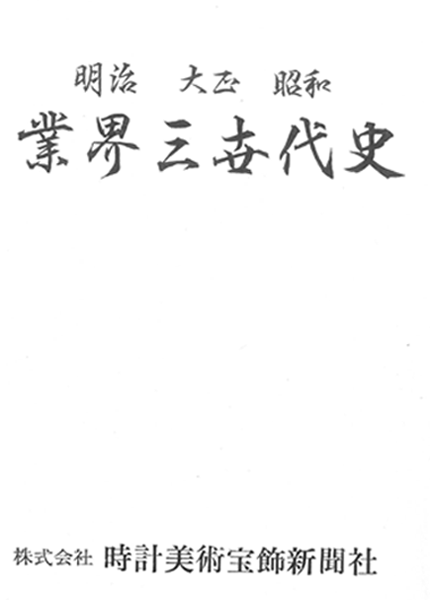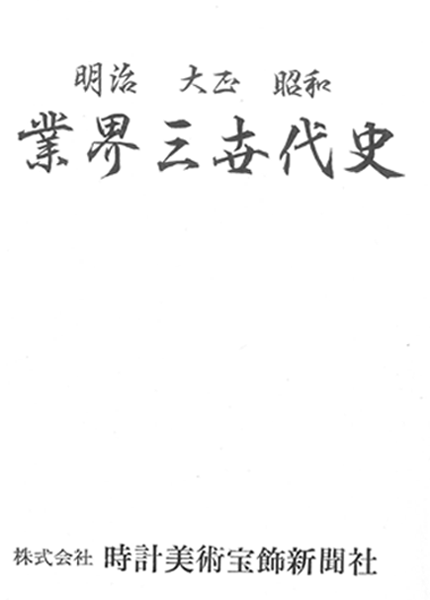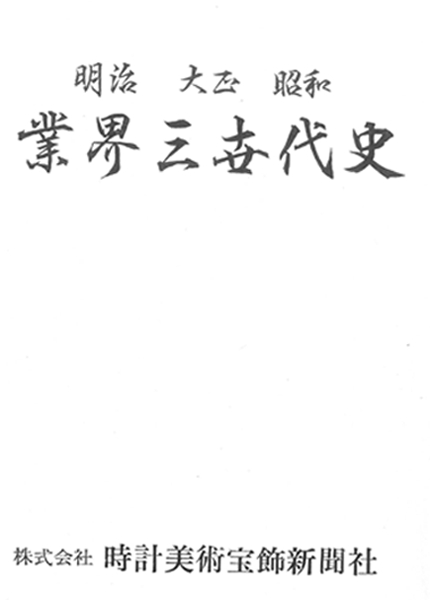| 深い馴染みの中島与三郎氏が起業家の立場で起死回生
《昭和三年》 本社主催の業者大会が終ったある日、中島さんが私の社を訪れて二人で懇談した事あった。話題は、「時計とその製造」という話になった。「シチズン時計の製造機械の全てが埃に埋もれているのは惜しい」という話題に移った。しばらくしてから、再度中島さんが私の社を訪問した際に、私が「シチズンの再生を進めてはどうか」と中島さんに自分の意見を言った時、初めて中島さんが私に次のように意中をもらした。
私はその話合いに基づいて、当時銀座一丁目の山崎商店と共に尚工舎工場の管理の立場にあった田中地金店を訪れて故人となった田中一郎社長に尚工舎に埋もれている時計機械部品の全部の譲り受けについて下話しをしてみたところ、「あれが役に立つならいくらでもいいよ、私が安田銀行に話をしてやる」といってくれたので、それを中島さんに報告した。それは昭和三年の秋頃だと記憶している。
そのような経過をたどった後、中島さんはシチズンの起死回生についての相談を金森時計店、小林時計店(川村支配人)、京都の大沢商会(森田支配人)を訪れて、それに協力を求めるためにはるばる単身出張したことがある。その時、私は旅先で中島さんに会って聞いている。このとき大阪の富尾時計店の社長に一応意見を求めたようである(これは現社長の話)。
かくして、昭和五年六月二十八日、資本金二十万円でシチズン時計株式会社を設立、自ら初代社長の座に就任したが、会社設立直前、初代社長就任を回避するような気持を私にもらしたことがあった。私は、「それは絶対グメですよ」といったことを覚えている。シチズン機械の譲り受け価格は、安田銀行の担保計算の関係で、最初は二十万円がとこを主張していたものだが、結局は五万を割った四万七千円という金額になったというから中島のおとっつぁんも、如何すべきものかとあとで苦笑したことがあるのを思い出した。
それから二、三年を経て、一応時計の生産体制も順調になったように見られた昭和八、九年の頃のことかと思う。シチズン時計会社への入社、または販売会社の設立という案を私に提唱されたことがあった。中島さんは、シチズンの再生復活を図っただけでなく、生産即消費という企業者の立場についても常に、苦慮されていたその事実を身近に感じたその時には、再度感動せざるを得なかった。
[注]中島与三郎氏については、私は深い馴染みを感じていたので、常におとっつぁんと呼んでいた。中島さんには、私と同年輩の倅がいて、下落合で薬剤店を経営していたので親交を計ってくれといわれたことがある。働手の私はその機会を得ることが少なかったまま戦争へ突入してしまったというのがその後のコースである。
それから後の同社は、現社長の山田栄一氏の努力が奏功して、シチズンは、日本時計工業の一翼を担い、堂々世界に雄飛しつつあるのは慶賀すべきであるが、その基礎を作ったのは、故人の中島おとっつぁん(与三郎)の功績で、特筆絶賛するに価するものがある。同社の現況の主なるものをあげれば要項次の如し。
シチズン時計の生産能力は、月間四十五万個、資本金三十億円、本社:東京新宿区角筈二丁目七十三番地。取締役社長山田栄一氏。工場=淀橋工場:新宿区戸塚町四―八五六番地、田無工場=東京都北多摩郡田無町一六五〇、販売所シチズン商事株式会社(東京都台東区御徒町一―十二番地、取締役社長山田栄一氏、専務取締役太田敬一氏。写真は、在りし日の中島与三郎氏。 |
|