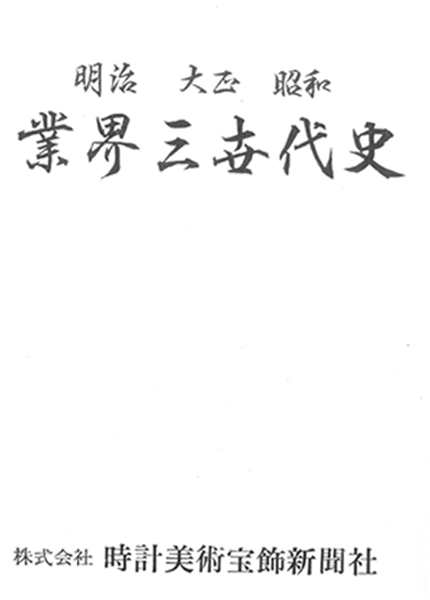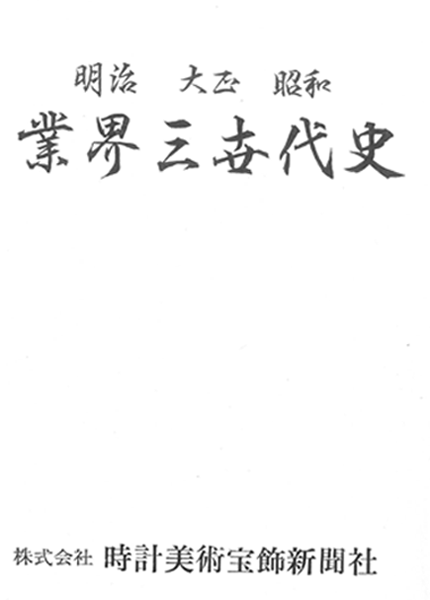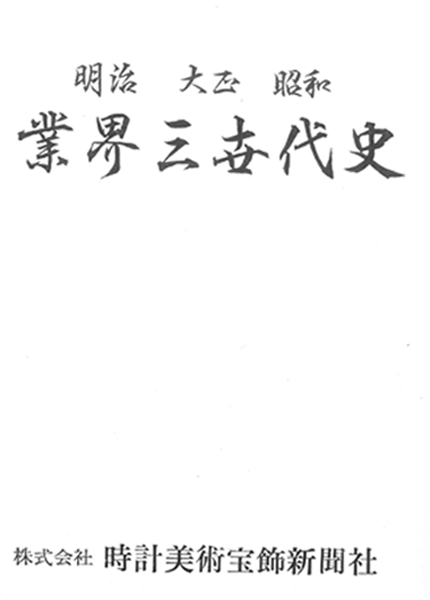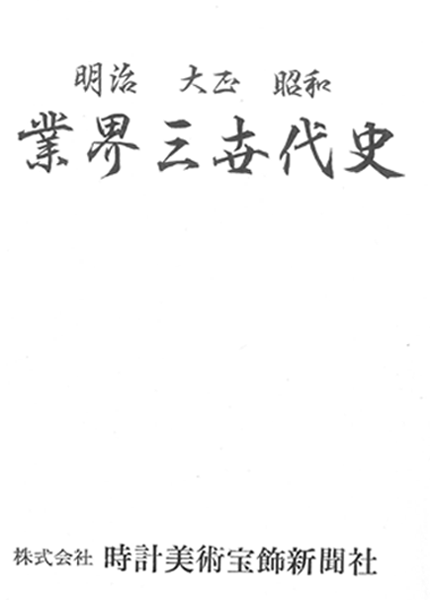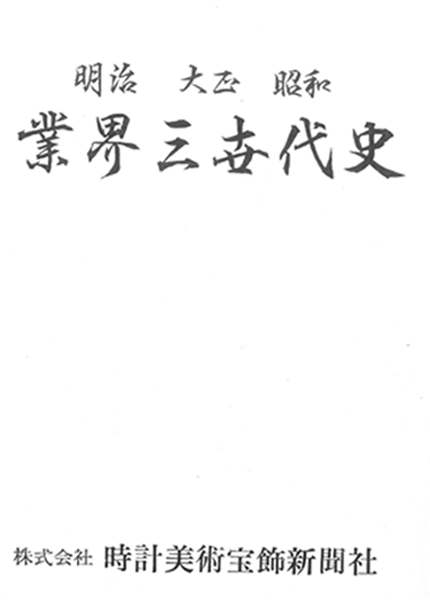|
���ʐ^���N���b�N�Ŋg�債�܂��B | Home |
| ���̃y�R���o������@�吳�N�� | ||
|
| �Z���\���u���̋L�O���v�Ɛ�`�����̎n�߂̍� | ||
|
| ��k�В���̉��l�̎��v�Ǝҋ~������ | ||
|
| �吳�N��̋ƊE�Ɗ֓���k�БO��̏� | ||
|
| �吳�N��ɐ��ꂽ���v�H�Ƃ̌a�H | ||
|
| ������������ƒm�荇�����o�H | ||
|
| ���v�o���h�����o���ꂽ�ŏ��̍� | ||
|
| �吳�\�ܔN�ɖ{���u���i���M�V���v���n�����������̋ƊE�̏� | ||
|
| �u���i���M�V���v�n�������̋Ǝ҂���̎x���� | ||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| page�F5 |