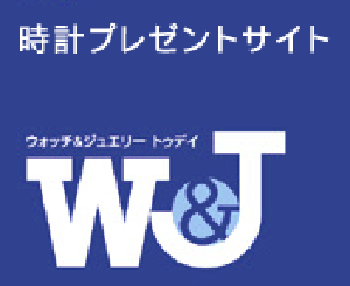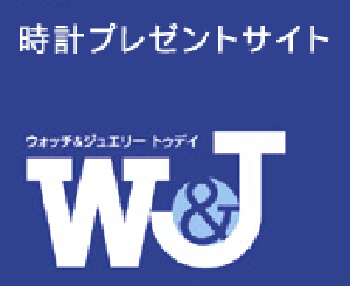| COIN-PARKING DELIVERY氏デザイン
日本製のメカニカルムーブメントを搭載したカジュアルウオッチブランド「セイコー5スポーツ」から、世界を舞台に活躍するアーティスト、COIN-PARKING DELIVERY(コインパーキングデリバリー)氏とのコラボレーション限定モデルを3月10日より発売す る。世界限定1,500本で、価格は52,800円。
COINPARKING DELIVERY氏 は、2018年に電車での移動時間 にスマートフォンを使い、指で絵を描きだしたことからクリエーション活動をスタート。現代人の必須アイテムでもある。
スマホを片手に、「今」というこの時代ならではの疑問や理想を落とし込んだ作品を制作、国内外で高い評価を得る。近年では、データのみならず造形、空間、ドローイング、海外のパブリックスペースの外壁など、さまざまな場所で独自の世界を構築している。
限定モデルは、SKXモデルのケース・ブレスレットをベースに、ダイヤルは「時間に縛られずに」という想いからあえて数字のないデザインに仕上げ、インデックスにはCOIN PARKING DELIVERY氏のアイコンである「白井さん」を 12時に、「片山さん」を6時に配し、人の感情の受け渡しを司る目と口から着想 を得た「eNrOll(エンロール)」のグラフィックがセットされている。
また、ダイヤルのベースには「一歩ずつ人生を登っていく」という意味を込めて、山のグラフィックをさりげなくデザイン。ケースとブレスレットはゴールドカラーとシルバーのコンビネーションで華やかにまとめ、COIN PARKING DELIVERY氏のこだわりを細部まで詰め込んだ、斬新かつアーティスティックなデザインが実現した。
https://www.seikowatches.com/jp-ja |
|