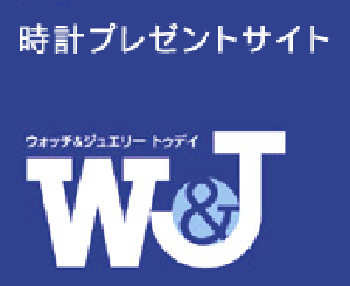| クロノグラフ、ラグジュアリースポーツウォッチ
腕時計と言えばスイス、ドイツ… 世界的に見ると日本の腕時計ブランドは少ない中で時計の販売業を行う合同会社MK.MARK(所在地:宮城県、菊地真代表)が日本製の腕時計【ELFOLK ALSTRO】(エルフォルク アルストロ)の先行予約販売を応援購入サイト「Makuake」で4月14日(金)より開始します。
この新作は、SEIKO社の日本製ムーブメント(VD53)を採用。基本部品には妥協せず高級素材を使用、風防(表面ガラス)には透明感、強度抜群のサファイアクリスタルを採用、ステンレスには強度が高い316Lステンレススチールを採用。
組立から完成検査、精度調整まで全て日本の宮城県仙台市の自社提携工場にて一つ一つを一級時計技能士が丁寧に組み上げます。
高級時計の代名詞としてクロノグラフ(ストップウォッチ機能)を搭載しているにもかかわらず、部品供給から組立までを自社で完結すること、無駄な中間コストを完全にカットすることによって実現した圧倒的なコストパフォーマンス。クロノグラフ、一目でわかる実用的な『曜日、24時間計』機能、安心の2年保証、耐水性2ATM。落ち着きのあるスタイリッシュでクラシックなデザインと機能性でビジネスシーンはもちろん日常使いとしてもお楽しみいただけます。
リターンについて
32,370円:超早割 35%OFF 先着30本限定
34,860円:早割 30%OFF 先着50本限定
37,350円:Makuake割 25%OFF 150本限定
39,840円:特割 20%OFF 200本限定
全てのリターン品に「Makuake」限定で専用ラバーバンドをプレゼントします。
※日本初ニューブランド腕時計【ELFOLK ALSTRO】4月14日に先行予約を開始
https://www.makuake.com/project/elfolk_alstro/ |
|