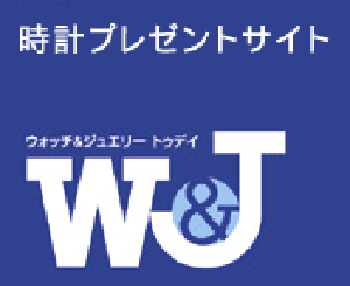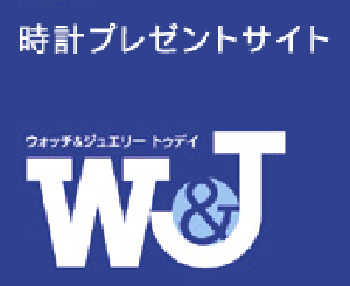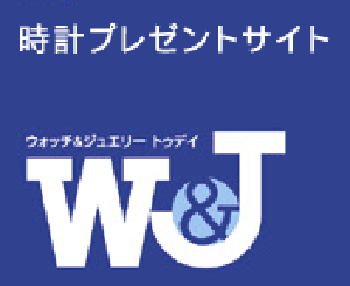|
※写真をクリックで拡大します。 | Home |
| 03/03(Fri) 受験を終えた人の応援キャンペーン | ||
|
| 03/02(Thu) 全国どこでも受講できるオンライン研修も | ||
|
| 02/20(Mon) メガネの上からサングラス”夜間運転に最適なオーバーグラス | ||
|
| 02/03(Fri) 花粉飛散量が昨年比200%越えも | ||
|
| 02/03(Fri) 新春恒例の眼鏡記者会「2023年新年賀詞交歓会」 | ||
|
| 02/03(Fri) 盛大に「2023年新春合同例会」 | ||
|
| 02/03(Fri) 「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」に加盟 | ||
|
| 02/03(Fri) メガネ移動車「JINS GO」発車 | ||
|
| 02/03(Fri) 顧客情報を全社で共有、付加価値の高いサービスを | ||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| page:9 |