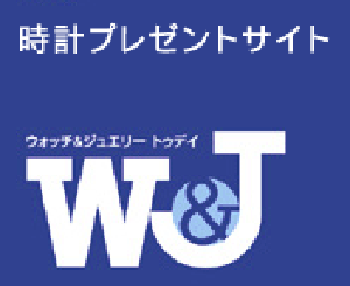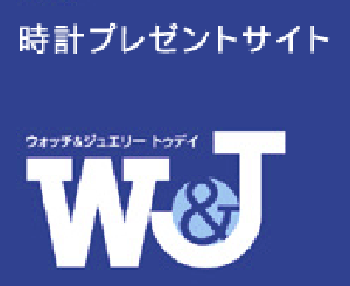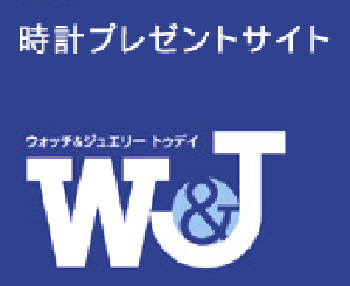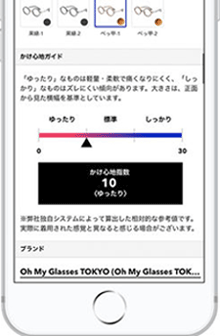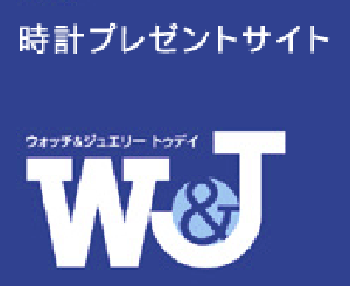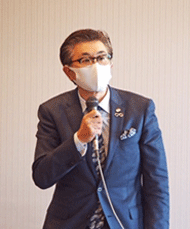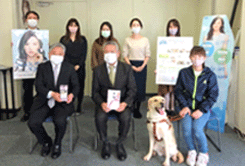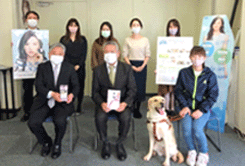 | 「Pureな愛(eye)をありがとうプロジェクト」
《シード》 一部上場企業の㈱シード(本社:東京、浦壁昌広社長)は11月26日、本社で公益財団法人アイメイト協会への寄付贈呈式を開催、「Pureな愛(eye)をありがとうプロジェクト」並びに2020年度株主優待制度を通じた株主からの気持ちを合計し、1,241万4千円を寄付した。
同社は、2011年7月より「Pureな愛(eye)をありがとうプロジェクト」を開始し、同社の主力製品である”シードPureシリーズ”の売上の一部をアイメイト協会や視覚障害サポートを行っている団体へ寄付することで、視覚障がいの方の社会的自立を支援してきた。2014年からは株主優待制度にも寄付コースを設けており、株主からの理解・賛同により、今年度も寄付を行うことができたもの。
同社は今後も国産の品質に則ったコンタクトレンズの製造販売を通じて、お客の“見える”をサポートするとともに、これからも視覚障害者とアイメイトとのパートナーシップから生まれる“見える”もサポートしていくとしている。
写真は、前列左より同社浦壁昌広社長、アイメイト協会の塩屋隆男代表理事。
コンタクトレンズのシード「SEED」 |
|