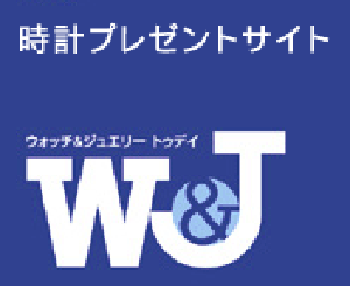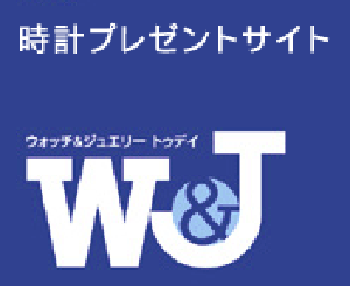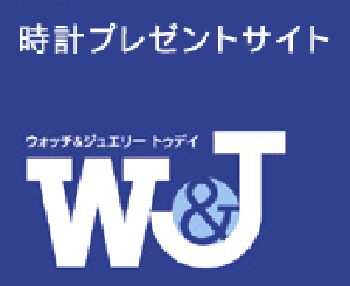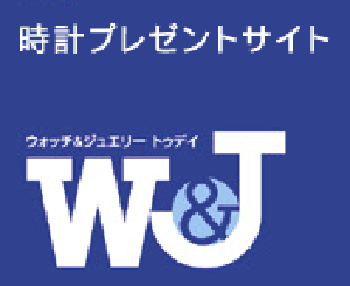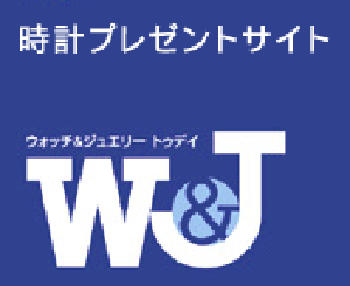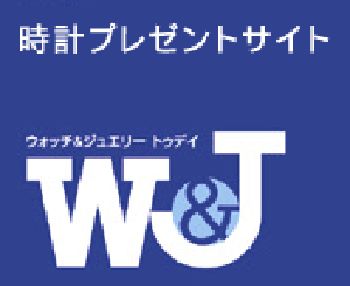| カリブ海の職人につながるストーリー HASUNA
RJCに加盟する ㈱HASUNAは、サークル型のウィルクス貝を使用した新作ジュエリー 「リュニック」を発表。 手軽に楽しめるシックで軽やかなネックレスを発売した。
雪豹のような美しい柄の「ウィルクス貝」は、カリブ海に面した中米の小さな国ベリーズ周辺でしかとれない珍しい貝。磨きあげることによって、艶のあるモダンな表情が生まれる。
また、HASUNAがウィルクス貝を仕入れることにより、職人たちに安定した収入をもたらし、仕事に対して大きな「誇り」を持つきっかけにもなっている。
それにより、同じ柄が世界にひとつとない、その唯一性がコレクションの魅力になってい る 。ネックレスは 79,200円、ピアスは 46,200円。
HASUNAのブランドコンセプトは、永 続的に受け継がれる 「PERPETUAL JEWELRY」のコンセ プトのもとに生み出される、時代が変わっても愛され続ける普遍的な美しさを持つジュエリー。素材には、エシカルダイヤモンドやエシカルゴールドを用い、デザインの美しさはもとより手に届くまでのストーリーすべてが美しいジュエリーを追求している。
https://hasuna.com/? |
|