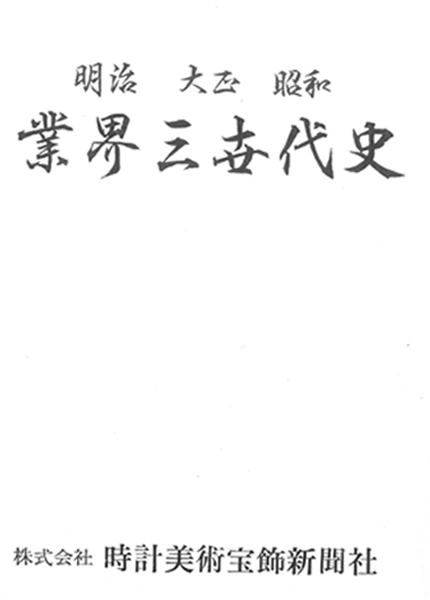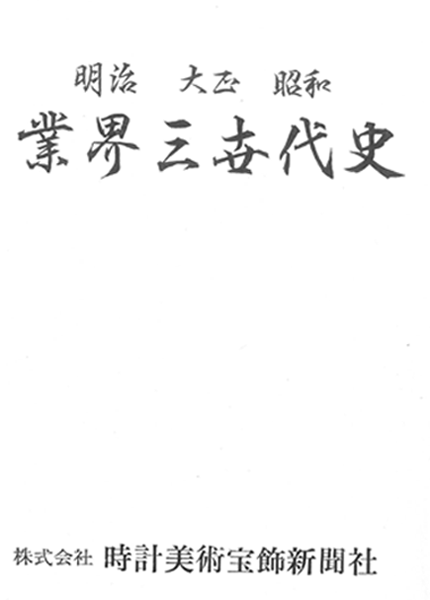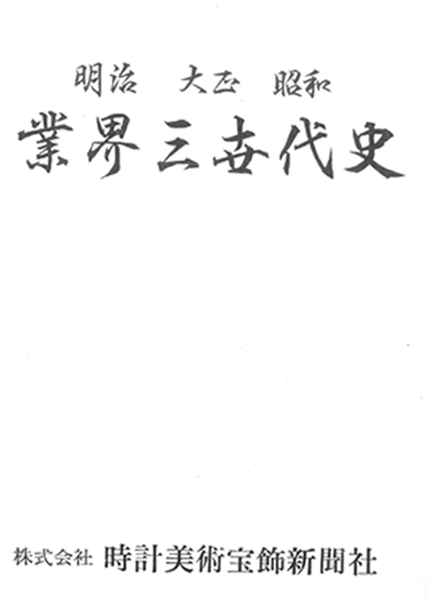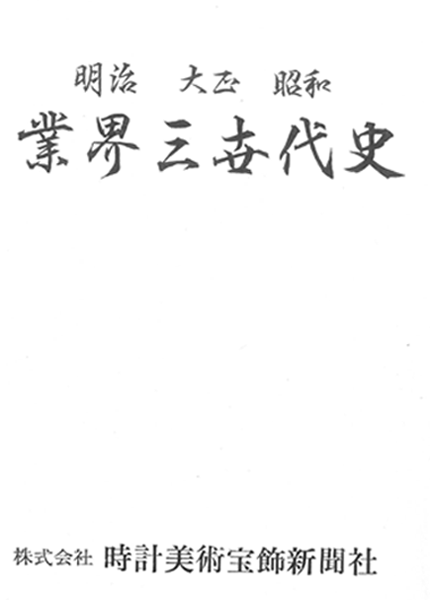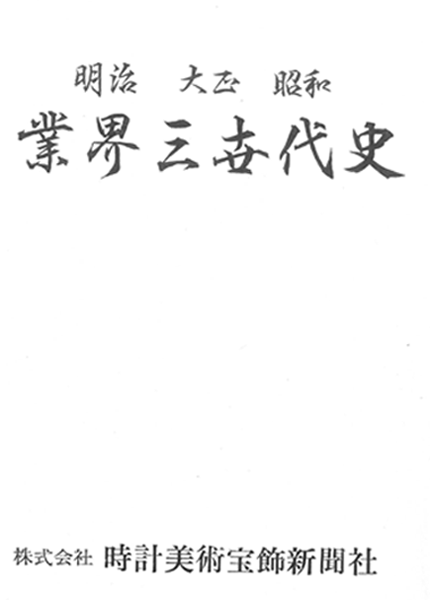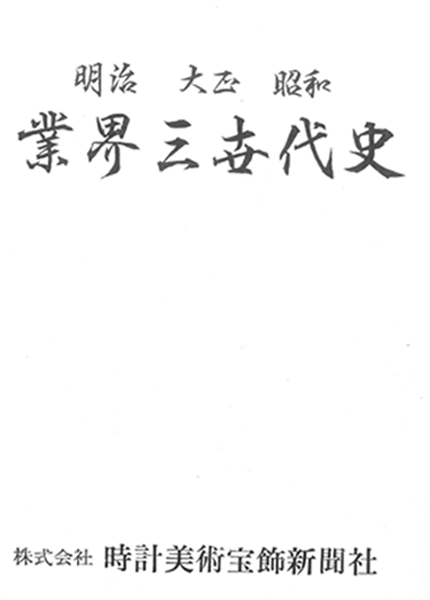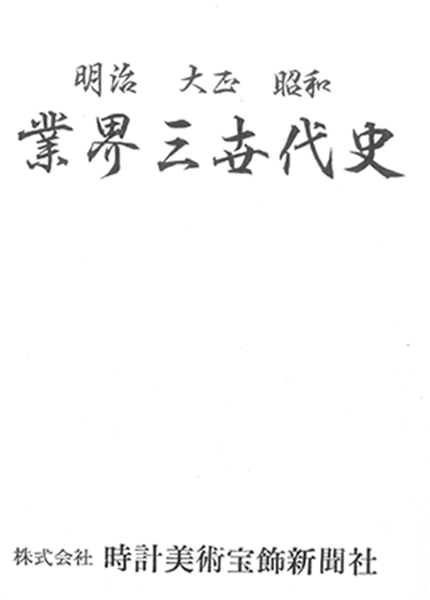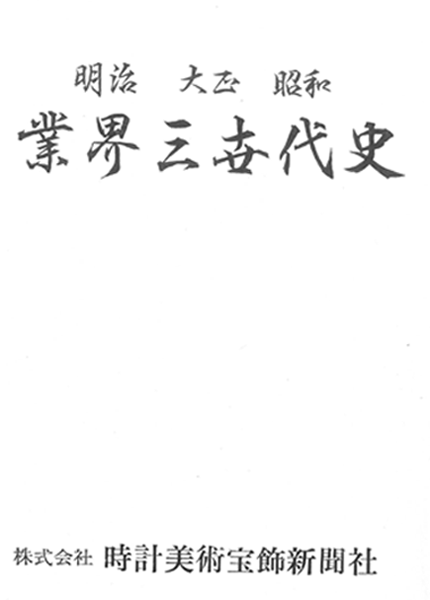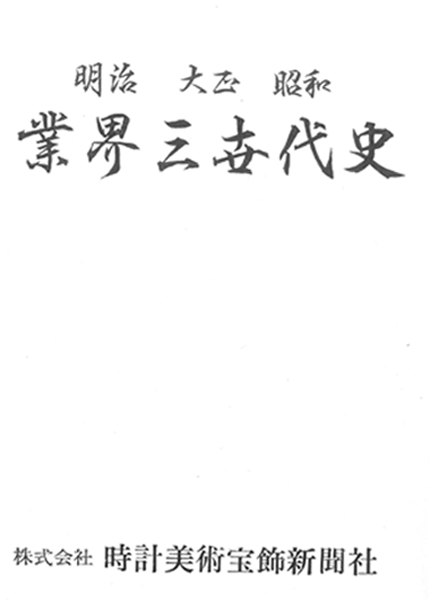|
���ʐ^���N���b�N�Ŋg�債�܂��B | Home |
| ���݂�Ǖ������V�䔒�̏��_�ʂ� | ||
|
| ���l�̐��b���������͉Ƃ̎j�� | ||
|
| ���͉��앺�q�̐l�i���ꑰ�����킹�錋�ʂł����� | ||
|
| �u���t�v�Ƃ��������X�g���������ݏ��B�œ������ | ||
|
| �����̎��v�����Q�̎x�z�l�A�̊�Ԃ� | ||
|
| ���J������̐��͑����̂��ƂȂ� | ||
|
| ���v���c�̂́u�����ܓ���v�Ƃ��̗֊f | ||
|
| �^�o���̋�������c�m�I�֏o�n�������̏� | ||
|
| �e���ȋ������v��r���������� | ||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| page�F4 |